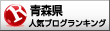営業時間、定休日などは変更されている場合がございますので信用しないでください。
変更された情報がございましたら、コメントでお知らせいただければ幸甚です。
古本屋さんで見つけた「第一阿房列車」を読了。
内田百閒の紀行文「阿房列車」シリーズに青森のラーメンのことが書かれているのを知り、予てよりぜひ読んでみたかった本だ。
1955年の新潮文庫版の復刊で、仮名遣い等は現代文に改められているので読みやすい。
青森のラアメンは「奥羽本線阿房列車 前章・後章」に登場します。
本を読むと著者の内田百閒と、同行した弟子のヒマラヤ山系(平山三郎)が青森の駅の近くでラアメンを食べたのは1951年(昭和26年)10月26日。
青森駅に12時34分に着いてから乗り継ぎ列車が発車する14時10分の間であろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
蕎麦屋へでも這入ろうかと云いながら歩いていたら、蕎麦屋より前に支那蕎麦の看板が目についた。私は支那蕎麦に余り馴染みはない。しかし山系の好物である。だから旅は道連れの仁義からおつき合いする。先年彼の地から帰って来た者に、本場の支那蕎麦はどうだと尋ねた。あちらにこんな物はありません。支那蕎麦の本場は新橋の烏森の辺りでしょうと云った。山系君も兵隊で行って北京を知っている。そちらが本場でないとすれば、帰って来てからラアメンを啜って曾遊を忍ぶと云うのも筋違いである。然るに中途半端な時、何か食べたかと聞くと、必ず支那蕎麦と答える。腹中に隙さえあれば支那蕎麦を食うと云うのは、何となくお行儀が悪く、意地きたなの様だが、青森まで来てそんな事を洗い立てても悪い。
~~~中略~~~
その内に支那蕎麦が出て来た。向こうのテーブルのお客はカツレツ弁当を食べている。一品料理も出来るらしい。焼け跡に建った新装の食堂である。山系君がこの支那蕎麦はうまいと教えてくれた。僕だってうまいさと云うと、そうではない、この麺が大変よろしい。ちぢれ工合と歯ざわりが、こんなのは滅多にありませんと云って、瞬く間に開いた大きな丼を平らげた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、戦後青森駅前に新装開店した食堂は何という食堂なのだろうか?今もある食堂なのだろうか?
その歯ざわりのいいちぢれ麺に合わせたスープは煮干しダシだったのだろうか?
あ~。食べてみたいな。
PR
*コメント投稿*